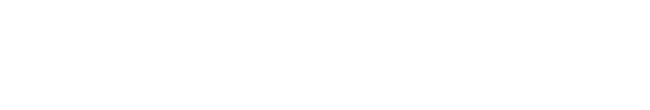本書の存在を私が知ったきっかけは、『週刊朝日』2021年12月3日号に載った、
内館牧子さんのエッセイ、「暖簾にひじ鉄 連載988 子供が働いた時代」
(36・37ページ)を読んだことでした。
この年の夏、内館さんのところに、青森に住む女友達からいろんな冊子等が届いた中に、
同書のチラシもあり、そのチラシの表・裏に印刷されていた
何枚かの写真に衝撃を受けたと、内館さんはお書きになっています。
青森の地方紙「東奥日報」のカメラマンだった工藤正市さんの写真の
どこに、内館さんは衝撃を受けたのでしょうか。
その理由を詳しく知りたいと思い、私はこの本を買いました。
「「街 冬から春へ」「街 夏から秋へ」「ある町、ある人」「山里 村の暮らし」「海辺 浜で働く人たち」と、全5章に収められた366点もの写真。
すべてモノクロなのですが、だからこそ、昭和25年から昭和37年までの「青森」の記憶を、どの写真からも鮮明に感じられたのだと思います。
昭和30年代前後という時代を懸命に生きた人々の心に思いを馳せると同時に、私はしばし、数十年前へと時間旅行をしたのです。
「『この時代だから』でもなく、『青森だから』でもなく、ここにあるのは人間のいとなみそのものだ」
-先に挙げたチラシに掲載されている、写真家であり、編集者でもある都築響一さんの言葉です。
青森出身でも青森に住んだことがある訳でもない私が、本書に感銘と衝撃を受けたのは、掲載された一枚、
一枚の写真に、ある普遍的な人間の営みを見たからにほかなりません。
写真に写っている人々の表情に、私たちと同じ、生きて行くことの悲しみ、辛さ、喜びを見たのです。
最後に、内館さんの次の文章を紹介しておきます。
「私たちの世代はまだ、肉体を酷使して生計を立てるつらさを、
子供が労働力に数えられる悲しみを知っている。
だから、そういう風景や人々の表情が胸に迫る」(37ページ)