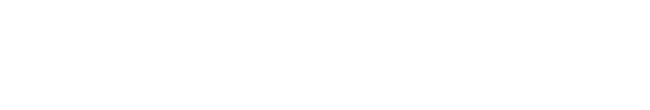20代前半の多感な時期を僕はアメリカと東京で過ごした。
アメリカでの大学生活が2年を過ぎた頃、当初からの夢であったレコーディング・エンジニアになるため大学を編入した。語学力も高校時代から合わせて計3年のアメリカ生活で十分に培われたと思っていたのだが、言語の壁をあまりにも軽く考えていたせいか、専門用語がバンバン飛び交う授業に驚くほどついていけなく、僅か半年でドロップアウト。そしてそのまま帰国し、故郷浜松に戻るくことなく東京へ出た。
アメリカにいた頃から学校以外の僕の居場所はBook StoreとCD Shop、週末に音楽仲間と一緒にPortlandへ出てボーリングというのがお決まりのコースだった。
週末のボーリング以外は東京へ出てからも変化なく、相変わらず居場所は本屋とCDショップだった。
90年代をアメリカと東京で過ごしたこともあり、アメリカではオンタイムで「オルタナティブミュージック」ブームに乗り、東京では「渋谷系」と称される音楽を聴き漁った。
それはまだスマートフォンもAmazonもGoogleもない時代だった。
最近、この頃のことをよく思い出す。
我ながらおっさんになったなぁ、と思うのは90年代を振り返って「あの頃が一番楽しかった」と思ってしまうことだ。そしてそれを堂々と口に出してしまうこと。これはイカン。
AmazonもGoogleもスマートフォンもない時代は、簡単に情報を得られない代わりに、手間隙かけて得た情報を大切に取り扱い、そしてその情報も密度が濃く、記憶への定着度も高かった。
堀部さんもこの本で『スマートフォンもSNSも、AmazonもGoogleも一度手にしてしまった以上、それを手放すことなど懐古趣味にほかならない』と綴っている。
そう、まさしくその通りで、それらが存在しない世界にはもう戻らない。
うまくお付き合いしながら、これから加速度的に変化する時代に対応しなければいけない。
さて、この堀部さんの『90年代のこと』は、そんな僕が過ごしてきた、「あの頃が一番楽しかった」と感じてしまう90年代のはなし。
共感したのは、【ヒップホップな本屋さん】のくだり。
見事なまでに的確な表現と素晴らしい文章なので引用する。
『すでに出尽くしたヴァリエーションの新しさよりも、過去のアーカイヴ発掘が新鮮だった一九九〇年代に青春を過ごしたぼくにとって、決定的な影響力を持ったのはほかでもないヒップホップだった。過去の情報を引用し、並び替え、別の意味を持たせる「編集」こそがクリエイティブな行為であるという発想の転換。それは音楽だけでなく他の分野にも応用できる「発明」だった。過去に出版された膨大な本を選択し、並べることで本棚という一つの世界観をつくることも同じように「編集」のひとつだ。』(P99)
どうだろう、これこそがいわゆるセレクト書店の本質なのでは無いだろうか。
「文脈棚」とか「セレクト書店」なんていうレッテルを貼るわけではなく、僕は全面的に肯定的にそう思うのだ。
いや、セレクトショップだけでなく、多くの一般的な書店における棚作りもこうあるべきなのだ。
同じ理由でヒップホップが好きで、書店の棚作りをしていたため、個人的にすごく共感した。
(こんなに論理的に表現することはとてもじゃないけどできないが・・・)
そして、最も感銘を受けたのは【一九九六年、本屋は僕の学校だった】の最後。
その際立った「セレクト」のセンスとコネクションを生かした品揃えで、多くの本好きに愛された「恵文社一乗寺店」の運営に疑問を持ちはじめた堀部さんが、なぜ恵文社を辞め、誠光社を立ち上げたのか。
『似たような品揃えの店が急激に増えはじめた。インターネットの普及とともに「セレクトする」ことの価値が急激に目減りしつつあった。「セレクト」することに専門知識やセンスが必要とされなくなるにつれ、効率よく事務作業をこなす人材が必要となりはじめていた。大型書店や巨大オンラインショップに反発することで注目された店だったはずなのに、いつの間にかグローバルなシステムを追いかけはじめていたのだ。』(P135~136)
恵文社の運営をしながら、こういった息苦しさを感じていた堀部さんは、本屋ではなく本とその周辺のカルチャーが好きだったとあらためて思い直し、
『効率よりもスピリットを、店そのものではなく本を売りにした店を作りたい。』(P138)
そう決意し、二十坪の誠光社を立ち上げたのだ。
『効率よりもスピリットを』
この言葉に、僕はいたく感銘を受けた。
当社のような書店はお客様へのサービス向上を考えると、効率も確かに大切。
しかし、スピリットをなくした書店は面白くない。
面白くないお店はお客様にとって必要ではない。
書店にとって何が一番重要か。
「読者=お客様」に向き合った書店で有り続けるために、シンプルに考え真摯に追求し続けたい。
今、書店経営が厳しいと言われる時代に、この本に出会えたことに感謝を。
アメリカでの大学生活が2年を過ぎた頃、当初からの夢であったレコーディング・エンジニアになるため大学を編入した。語学力も高校時代から合わせて計3年のアメリカ生活で十分に培われたと思っていたのだが、言語の壁をあまりにも軽く考えていたせいか、専門用語がバンバン飛び交う授業に驚くほどついていけなく、僅か半年でドロップアウト。そしてそのまま帰国し、故郷浜松に戻るくことなく東京へ出た。
アメリカにいた頃から学校以外の僕の居場所はBook StoreとCD Shop、週末に音楽仲間と一緒にPortlandへ出てボーリングというのがお決まりのコースだった。
週末のボーリング以外は東京へ出てからも変化なく、相変わらず居場所は本屋とCDショップだった。
90年代をアメリカと東京で過ごしたこともあり、アメリカではオンタイムで「オルタナティブミュージック」ブームに乗り、東京では「渋谷系」と称される音楽を聴き漁った。
それはまだスマートフォンもAmazonもGoogleもない時代だった。
最近、この頃のことをよく思い出す。
我ながらおっさんになったなぁ、と思うのは90年代を振り返って「あの頃が一番楽しかった」と思ってしまうことだ。そしてそれを堂々と口に出してしまうこと。これはイカン。
AmazonもGoogleもスマートフォンもない時代は、簡単に情報を得られない代わりに、手間隙かけて得た情報を大切に取り扱い、そしてその情報も密度が濃く、記憶への定着度も高かった。
堀部さんもこの本で『スマートフォンもSNSも、AmazonもGoogleも一度手にしてしまった以上、それを手放すことなど懐古趣味にほかならない』と綴っている。
そう、まさしくその通りで、それらが存在しない世界にはもう戻らない。
うまくお付き合いしながら、これから加速度的に変化する時代に対応しなければいけない。
さて、この堀部さんの『90年代のこと』は、そんな僕が過ごしてきた、「あの頃が一番楽しかった」と感じてしまう90年代のはなし。
共感したのは、【ヒップホップな本屋さん】のくだり。
見事なまでに的確な表現と素晴らしい文章なので引用する。
『すでに出尽くしたヴァリエーションの新しさよりも、過去のアーカイヴ発掘が新鮮だった一九九〇年代に青春を過ごしたぼくにとって、決定的な影響力を持ったのはほかでもないヒップホップだった。過去の情報を引用し、並び替え、別の意味を持たせる「編集」こそがクリエイティブな行為であるという発想の転換。それは音楽だけでなく他の分野にも応用できる「発明」だった。過去に出版された膨大な本を選択し、並べることで本棚という一つの世界観をつくることも同じように「編集」のひとつだ。』(P99)
どうだろう、これこそがいわゆるセレクト書店の本質なのでは無いだろうか。
「文脈棚」とか「セレクト書店」なんていうレッテルを貼るわけではなく、僕は全面的に肯定的にそう思うのだ。
いや、セレクトショップだけでなく、多くの一般的な書店における棚作りもこうあるべきなのだ。
同じ理由でヒップホップが好きで、書店の棚作りをしていたため、個人的にすごく共感した。
(こんなに論理的に表現することはとてもじゃないけどできないが・・・)
そして、最も感銘を受けたのは【一九九六年、本屋は僕の学校だった】の最後。
その際立った「セレクト」のセンスとコネクションを生かした品揃えで、多くの本好きに愛された「恵文社一乗寺店」の運営に疑問を持ちはじめた堀部さんが、なぜ恵文社を辞め、誠光社を立ち上げたのか。
『似たような品揃えの店が急激に増えはじめた。インターネットの普及とともに「セレクトする」ことの価値が急激に目減りしつつあった。「セレクト」することに専門知識やセンスが必要とされなくなるにつれ、効率よく事務作業をこなす人材が必要となりはじめていた。大型書店や巨大オンラインショップに反発することで注目された店だったはずなのに、いつの間にかグローバルなシステムを追いかけはじめていたのだ。』(P135~136)
恵文社の運営をしながら、こういった息苦しさを感じていた堀部さんは、本屋ではなく本とその周辺のカルチャーが好きだったとあらためて思い直し、
『効率よりもスピリットを、店そのものではなく本を売りにした店を作りたい。』(P138)
そう決意し、二十坪の誠光社を立ち上げたのだ。
『効率よりもスピリットを』
この言葉に、僕はいたく感銘を受けた。
当社のような書店はお客様へのサービス向上を考えると、効率も確かに大切。
しかし、スピリットをなくした書店は面白くない。
面白くないお店はお客様にとって必要ではない。
書店にとって何が一番重要か。
「読者=お客様」に向き合った書店で有り続けるために、シンプルに考え真摯に追求し続けたい。
今、書店経営が厳しいと言われる時代に、この本に出会えたことに感謝を。