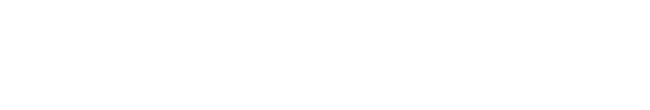「自分の青春時代を描くと、思いの丈ならぬ“思い出の丈”を
情感たっぷりに描きがちですが、そうではなく、同世代以外の
人にも伝わるように書きたかったので、落語の地噺のように
所々に当時の説明を挟みました」
著者の姫野カオルコさん(幻冬舎刊『昭和の犬』で、第150回直木賞を受賞)は、『オール讀物』2020年12月号の「ブックトーク」(223ページ)で、このように語っています。
この言葉通り、本書は1958年生まれの姫野さんが、60代の主人公・乾明子(いぬい・めいこ)に自らの高校時代を託して(重ねて)描いた青春小説です。
当時を彩ったテレビ番組や音楽雑誌、あるいは人気アーティストの名前等(それらに対する説明は、いかにも姫野さんらしい語り口です)が散りばめられていて、姫野さんと同世代の皆さんは、懐かしさに胸がいっぱいになることでしょう。ですが、本小説の主題は寧ろ、青春の痛みや辛さを描き出すことにあります。
暗い家庭に育ち、居場所が学校だけだったという明子の心情は、
どんな世代の人たちにも、痛切に響くのではないでしょうか。
スマホもコンビニも無かった時代の青春は、今の10代の方たちには新鮮に映るかもしれませんが、この小説で浮かび上がる青春の残酷さと10代だからこその繊細な感情は、今の時代にも共通するもののはずです。
本書のオビには「あざやかによみがえる高校時代。フツウな青春小説」
とありますが、私は本書で明子が送った青春が、決して「普通」だとは思いません。
なぜなら、ここには、明子という存在だからこそ経験し得た10代の日々があるからです。その価値を共有していただけたら、と願っています。