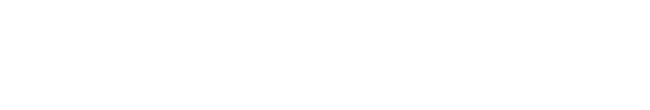ブルシャスキー語、ドマーキ語、コワール語、カティ語、シナー語、カラーシャ語、カシミーリー語……
どれも著者の研究対象である、話者人口の少ない言語だ。
どれかひとつだけでも耳にしたことがある人はどのくらいいるだろう?
言語学という学問自体あまり馴染みがないのだけれど、それにしたってこの本に出てくる言語は、馴染みのなさが頭ひとつ抜けている。
そのとっつきにくさを和らげてくれるのは、砕けた雰囲気と豊富な語彙とユーモアとぼやきが入り混じった著者特有の語り口だ。
しかしフィールド言語学者でありながら現地嫌いとはこれ如何にと思ったが、一読すればなんとなく合点がいく。
距離感の合わない異文化で四苦八苦し、遠巻きに、もしくはわざわざ寄ってきてバカにされ、バスを降りた途端○○を踏み、ぼったくり民家に遭遇し……
一度二度逢っただけでも心が折れそうな出来事は枚挙に暇がない。
それらに耐えてなお調査を続けても、進捗がはかばかしくないことも多々。
日本で生まれ育った身からすれば過酷と形容したくなる環境での調査は心身を削る。
それでも、場合によっては外出禁止令が出ているような危険な地域へ赴く必要もあるのだ。
そりゃぼやきのひとつやふたつやみっつ出る。
もちろん、研究に伴う厳しいあれこればかりを綴っているわけではない。
語り継がれる物語から読み取ることができる文化的背景、それぞれの信仰のこととそれにまつわることば、言語の血統(高貴とか雑種とかいうのではない)について、言語が『消える』ということについて。
現地調査から掬い取った、知的好奇心をくすぐられるエピソードがそこかしこに散りばめられている。
山越え谷越え言語を追い求める地味で地道な研究活動の記録と、研究に邁進する中で生まれ出た思考。
時にドライに時にウェットに、淡々としているようで言語へ真摯に向き合う熱も感じる、不思議な読み心地のする一冊。