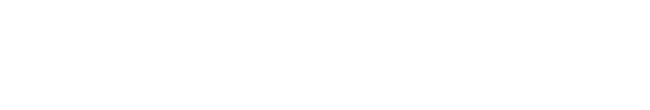正直言って賛否両論あるだろうなぁ、と思った。
言葉の選択が洒落ているから、今風で軽く感じてしまうかもしれない。
本を読んだときに、それをどう感じるかは人ぞれぞれ。
「明け方の若者たち」を読んで、斜に構えているなぁと思う人もいれば、新しいと感じる人もいるだろう。
小説の良い悪いは、正直僕にはわからない。
正確に評価出来る知識もない。
ただ感じたままに発言することが許されるのであれば、僕はこの「明け方の若者たち」で、思った以上に衝撃を受けた。多少大げさに言うのであれば、中学生のときに初めて村上春樹の「ノルウェイの森」を読んだときの驚きを思い出した。
そう、まさに作中にも出てくる、
『記憶を呼び起こすスイッチというものが、世の中にはいくつも設置されている』
という一文の通り、この小説が僕の記憶を呼び起こすスイッチとなった。
誰しも若かりし頃、最初で最後の恋と思って誰かを好きになったことがあるのではないだろうか。
そんな恋が一方通行に変わってしまったときの切なさが見事に描かれている。
「一緒にいたいね」と告げると「そうだね」
「好きだ」と伝えて返ってくる言葉が「ありがと」
期待していた返事とは違った言葉。
『こちらの「会いたい」には応えないのに、相手の「会いたい」には拒否権のない関係』
その人の仕草とか、声とか、不機嫌な顔も、全て好きになってしまうと、ひどいことをされても許すとか許さないとかじゃなくて、嫌いになれない。
もう完全に泥沼なんだけど、死ぬほど好きだった人との別れに絶望して自分の時間は完全にストップしてしまうのに、それなのに、日々は関係なく淡々と続いていく。
明け方の若者たちは、それでもいつか泥沼から這い上がってきて、もう一度 ”打席に立とうとする”。
「ここじゃないどこか」
「こんなハズじゃ、なかった」
誰もが一度は思ったことがあるであろうその感覚を思い起こさせるが、『明け方の若者たち』を読んで、改めて若かった頃の自分を振り返り、色々とそれなりに頑張ったんだなぁと昔の自分を褒めてやりたくなった。
カツセマサヒコという作家は、今後新しい時代をリードする作家になるのかもしれない。
強くそんな予感がしました。